震災で山梨県に避難し活躍している方々や避難者を支援する団体などに各種情報を元に絆ネットワークのメンバーが取材し、レポートとしてまとめました。

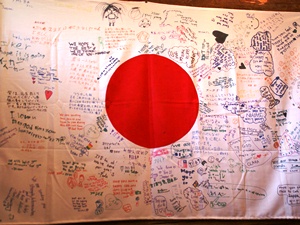

被災時の状況やこの取組みを行うようになった経緯
私たちNPOは、以下のミッションを掲げ活動を行っています。
地域資料デジタル化に関する研究と実践
地域資料デジタル化に関する普及啓発
図書館・博物館等の学習施設の情報化およびサービスに資する事業
その他、本会の目的を達成するために必要な事業
今回、平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって多くの人命と財産が失われましたが、その中で人災だけでなく、公共図書館などにおいて地域の歴史や文化を伝える貴重な資料も数多く失われてしまいました。私たちNPO法人地域資料デジタル化研究会では、私たちにできることとして、図書館で被災した地域資料をデジタル化技術を用いて救出できないだろうかという議論が生まれました。
左の写真は被災後 間もない陸前高田市立図書館です

食品の提供をとおして心をつなぐ
「フードバンク山梨」は東日本大震災直後から市町村の福祉課や社協からの依頼を受け、震災により県内へ避難された方々へ食品などの提供を行なっている。
当初は、企業・団体や個人の方から寄せられた食品などを出来る限り避難者の依頼にそうように「フードバンク山梨」が準備し、市町村の福祉課や社協の方がそれぞれの避難先に配達していたとのこと。
現在は「フードバンク山梨」が配達もしながら、食品の提供を続けている。
また、支援者から送られる荷物には、食品とともに避難者への声掛けのお手紙も添えられているとのことで、避難者と県民の心を食品の提供をとおしてつないでいる。
左の写真は、食品を送り先ごとに仕分ける様子。

福島県双葉郡大熊町。福島原発の1号機から4号機が立地するその町に自宅を持つ高橋清さんは、被災後、笛吹市で避難生活を送っている。高橋さんは、来県当初から県内のマスコミ取材にできる限り応じてきた。それは、未曽有の大災害とそれに続く原発被害の実情を、体験者の立場で伝え、理解してほしいという一途な思いからである。そしてまた、東海、東南海、富士山と今後起こりうる自然災害と無縁ではない山梨県の皆さんに、自分の話が少しでも参考になるようにと願いながら高橋さんは語る。
絆ネットワークの取材メンバーが高橋さんにお話をうかがったその日は、ちょうど節分の2月3日。現れた高橋さんは、「ここに来る前、富士川町の昌福寺の豆まきに、福島県人会から参加してきました。これまでの厄災を払うように、気持ちをこめて豆をまきましたよ。」と。


気仙沼に単身赴任していて被災した「先生」が再起を誓う
後藤照夫さんは、東京製菓学校や気仙沼で支援学校の講師を務めていたことから「先生」と呼ばれている。過去に心臓のバイパス手術をしていて、被災時は薬と保険証だけ持って逃げ、40年来の友人(富士吉田市在住)に誘われ山梨に来て、友人の親族が提供してくれた元民宿を借りてパン屋さんを開店させた。
ここで独自に開発したクリスタルカーボンを練り込んだパンやロールケーキなど他に類を見ない商品を販売している。地元のパン屋さんと違う商品なので、噂を聞きつけて遠方より来るファンも多く、これで鳴沢村を有名にして恩返しをしたいとのこと。
左の写真は「洋菓子とパン工房 テルゴ」の入口
